〜BL-5A, AR-NW12Aを用いた
ATP加水分解サイクル中間体の構造解析〜
2008年10月8日
東京大学大学院医学系研究科の仁田亮さん、廣川信隆教授のグループは、フォトンファクトリーのBL-5A, AR-NW12Aを用いて、細胞内のモータータンパク質であるキネシンのATP加水分解サイクルの中間体の構造解析に成功し、キネシンの動作機構の全容の解明に大きく前進しました。
キネシンは、ATPの加水分解エネルギーを使って微小管に沿って移動し、生命活動に必要なさまざまな物質を輸送する分子モータータンパク質です。廣川研究室では、キネシンの原子レベルの動作機構を解明するために、単頭型のキネシンモーターであるKIF1Aの構造解析を行い、これまでに、Mg-ATP結合状態、Mg-ADP結合状態、およびATP加水分解中間体の構造(Mg-ATPからMg-ADPへの移行状態)を報告してきました (Kikkawa et al., Nature, 2001; Nitta et al., Science 2004) 。これに関しては、以前にNews@KEK『「運び屋」キネシンの動くしくみ』でも紹介されています。今回構造解析に成功したのは、もう一つの重要な中間体であるADP/ATP交換過程(Mg-ADPからMg-ATPへの移行状態)の中間体です。これにより、キネシンのATP加水分解サイクルを全て解くことに成功しました。
KIF1Aは、ADP結合状態では微小管と緩く結合して微小管上を一次元ブラウン運動しながら次の結合サイトを探します。そして、ADP/ATP交換過程において微小管との強い結合に移行します。この際、KIF1Aの結合は前へ移動しながらのものとなり、これがモノマー型モーターの方向性の源となっています。また、このADP/ATP交換過程はキネシンのATP加水分解サイクルの律速となっており、キネシンがレールである微小管と結合する事によってこの過程が104倍以上促進されることがわかっています。つまり、このADP/ATP交換過程は、キネシンの化学エネルギーの無駄な損失を抑制する為の化学的チェックポイントになっており、レール側との結合によってこの抑制が解除されるというしくみになっています。さらに、この過程は、二量体型のキネシンが二足歩行する際に、必ず片方の足が微小管についているようにするためのゲートになっており、その意味でも構造解析が待たれていました。
ADP放出がATPサイクルの律速となっている、つまりキネシンがADPと強固に結合していることがこのサイクルの動作機構の鍵のひとつです。今回解析した構造により、ADPはMgおよびその配意水の密な水素結合ネットワークにて覆われ(Mg-water cap)、周囲の構造とともに、ATPポケット内に強固にトラップされていました。さらに、この部分は、Switch I、Switch IIと呼ばれる構造を介して、L7と呼ばれるβヘアピン構造にアンカリングして安定化させていました。微小管は、L7の先端部分 (Microtubule-sensorと名付けました)を認識してキネシンと結合し、静電的引力によりキネシンを微小管側に引っ張ります。すると、このL7にリンクされていたADPの周りの結合が外れ、Mg-water capが外れ、ADPが出て行くというしくみになっていることがわかりました。これにより、微小管による化学的チェックポイントのリリースの分子レベルの機構が、原子レベルで明らかになりました。
この研究成果は、Nature Structural & Molecular Biology誌2008年10月号に掲載されました(オンライン版は9月21日に公開)。
Ryo Nitta, Yasushi Okada and Nobutaka Hirokawa : Structural mode for strain-dependent
microtubule activation of Mg-ADP release from kinesin. Nature Structural
and Molecular Biology, 15, 1067 - 1075 (2008).
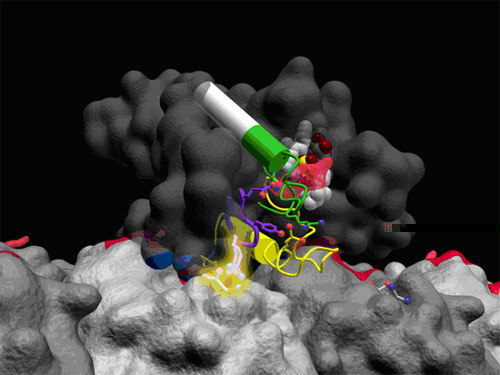
| キネシンKIF1Aと微小管(図の下側の2色のグレーの部分)の結合部位。 紫がL7(先の光っている部分がMicrotubule-sensor)、緑がSwitch I、黄色がSwitch II、ADPの上に被さっている赤いものがMg-water cap。 |
by pfw3-admin@pfiqst.kek.jp