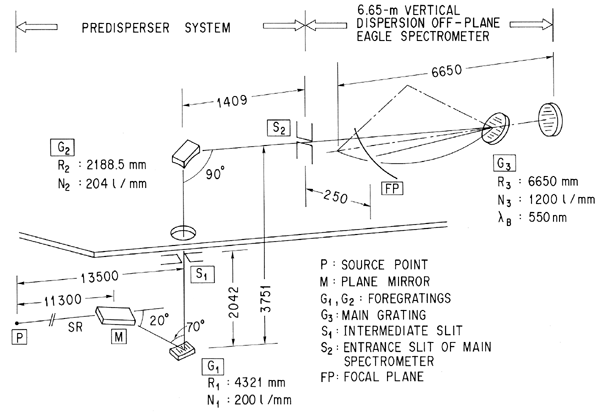
図1.BL−12Bの光学系.
担当者: 伊藤 健二
5644(PHS:4418)
kenji.ito@kek.jp
BL-12B 高分解能極紫外垂直分散型分光器(6VOPE)の閉鎖につい て 2005/06/06
BL-12B高分解能極紫外垂直分散型分光器(6VOPE)は原子・分子のイオン化しきいエネルギー近辺における光吸収スペクトルを世界最高の分解能で測定し、そこでのイオン化ダイナミクスを明らかにすることを目的として、PF創設時の1983年、波岡武東北大学科学計測研究所教授(当時)を代表者とする建設グループにより詳細な検討が行われ、島津製作所により製作納入された。日本では初の6mクラスの直入射型分光器であり、さらに高次分光に必要な次数分離用に開発された前置分散系の調整に多少時間を費やしたが、1985年春に写真分光でE/ΔE〜2.5×105の分解能を達成し[1]、光電測光では1988年にE/ΔE〜1.5×105の分解能に到達[2]することができた。これらは本分光ラインが目指す原子・分子の光イオン化しきいエネルギー領域で、回折格子分光器として世界最高分解能である。BL-12Bでは、希ガス原子、簡単な分子の光吸収スペクトルが測定され、エネルギー準位および吸収断面積に関する詳細な分光学データが得られた。特に、希ガス原子の光イオン化しきい値近辺の高分解能光吸収断面積測定法の確立はab
initio計算へ大きな刺激を与えた[3]。また、超音速分子線を用いて測定された極低温での光吸収断面積は、希薄な星間雲での物理化学系における反応ダイナミクスを理解するため、あるいは宇宙に打ち上げられた分光施設から送信されてくるスペクトルを解釈するための貴重なデータを提供してきた[4]。さらに、金属蒸気の光吸収断面積測定では、金属蒸気の試料密度の測定を含め新たな測定法を提起した[5]。6VOPE
は、分解能の点ではレーザーに一歩譲るが、広いスペクトル範囲を一度にカバーできる利点を活かす測定が行われた。写真法と超音速分子線を組み合わせたN2[6]およびCO[7]の光吸収スペクトル測定とその多元量子欠損理論的解釈についての発表は、回折格子分光器の性能を最大限に発揮させた二原子分子分光の集大成と言える。また、Imperial
Collegeで開発された真空紫外用フーリエ分光器と6VOPEを組み合わせたNOおよびO2の超高分解能測定も特筆すべき研究である[8]。これらの研究によりBL-12Bの成果として発表された論文はおよそ50を数える。これは決して多い数ではないが、すべて6VOPEの高分解能特性を活かした成果である。データ解析およびその解釈には年月がかかり、論文を量産できる研究分野ではないことも論文数が必ずしも多くない理由の一つであると考えられる。現に、10年前に測定された結果が昨年から今年にかけて発表されている例も見られる。
6VOPEは、そのユーザー数は限られていたが、PF創成時としてはユニークな単一目的の分光施設であり、アクティブなユーザーにも支えられ多くの学術的に高い成果を得ることができた。しかしながら、最近は需要が減少し、ここ数年は課題申請がない状態が続いている。これは、一つには偏向電磁石を光源とするBL-12Bで研究できる対象はほぼ終了したことを意味すると理解できる。原子・分子の高分解能分光に関する研究以外への転用も検討されたが、偏向電磁石を光源としかつ世界高分解能を目指す設計になっているために、光強度が最高分解能で104-5光子/秒と非常に低くその可能性は小さいと判断される。BL-12Bにおける分解能と同程度で6−7桁高い光強度が供給されるビームラインがすでに、米国およびフランスで実現していることも見逃せない事実である。そこでは、アンジュレーター光源と直入射型分光器の組み合わせによりこのような高性能が実現されている。
2000年の外部評価報告書のBL-12Bの今後のあり方について、「すでに、述べたように本BLの使命は終了したと言える。今後は、この分解能を有し、大強度の光を提供するBLを建設することが極紫外領域における研究を世界レベルに保つためには重要である。具体的には、アンジュレータを光源とする6mあるいは10mクラスの直入射型分光器を備えたBLの建設である。極紫外領域は、物質の性質を決定する価電子を研究するためには欠かすことのできない光であることは、言うまでもないことである。」という提言をいただいた。現時点においてユーザーが居ないことに鑑み、BL-12Bを閉鎖することとした。このことにより、1)このBL-12Bを維持するためのマンパワーを他のよりアクティブなビームラインへつぎ込めること、2)直線部増強計画で玉突きで追い出されたビームラインの受け入れ候補地や狭小な作業空間の改善、などのメリットもある。
上述のコメントの最後の一文にもあるとおり、極紫外領域の高分解能分光施設の重要性は言うまでもない。原子・分子科学のみならず固体・表面物性研究分野での需要も考慮し、現在PFで整備されつつある直線部増強計画の一環としてアンジュレータを光源とする直入射型ビームライン建設へと続いていくことが望まれる。光強度の増大により、光吸収スペクトルのみならず、その後続過程で生成する光電子、光イオン、断片種あるいは発光を検出することにより、光と原子・分子との相互作用をダイナミクスとして捕らえることが可能となってくる。固体・表面物性研究の分野では、フェルミ準位近傍の低エネルギースケールにおける電子状態を高分解能光電子分光により直接観測することにより、超伝導、巨大磁気抵抗、金属―絶縁体転移など、強相関電子系に特有な物性あるいはその発現機構の研究が期待される。また、可変偏光のアンジュレーターを導入することにより、たんぱく質やDNAなどの生命体を構成する分子を対象とした自然円二色性の測定、またカイラル分子の光解離など、価電子領域での興味深い研究分野が開ける。
[1] K. Ito et al. Appl. Opt. 25, 837 (1986).
[2] K. Ito, K. Maeda, Y. Morioka and T. Namioka, Appl. Opt. 28, 813 (1989).
[3] K. Maeda, K. Ueda and K. Ito, J. Phys. B26, 1541 (1993).
[4] http://cfa-www.harvard.edu/amdata/ampdata/cfamols.html
[5] K. Maeda et al. J. Phys. B30, 3159 (1997) and B33, 1943 (2000).
[6] Jungen et al, J. Chem. Phys. 118, 4517 (2003)
[7] M. Eidelsberg et al, J. Chem. Phys. 119, 292 (2004).
[8] K. Yoshino et al, J. Chem. Phys. 109, 1751 (1998); T. Imajo et al.
J. Chem. Phys. 112, 2251 (2000); T. Matsui et al, J. Molec. Spectrosc.
219, 45 (2003).
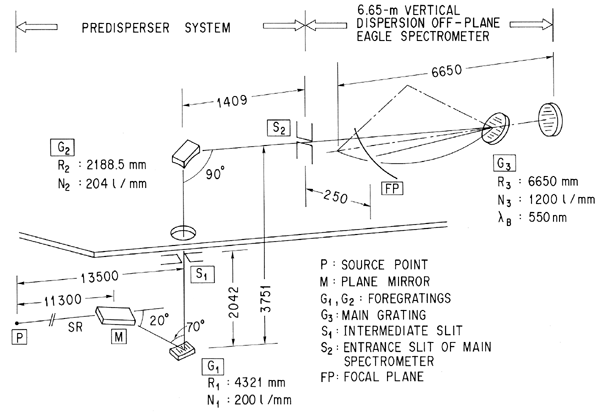
| 光学系 | 添付図参照 |
|---|---|
| エネルギー領域 | 5−30 eV(注1) |
| 分解能 | 25万、15万(注2) |
| ビームサイズ | |
| ビーム強度 | 5×104 photons/sec @10×10 μmスリット(注3) |