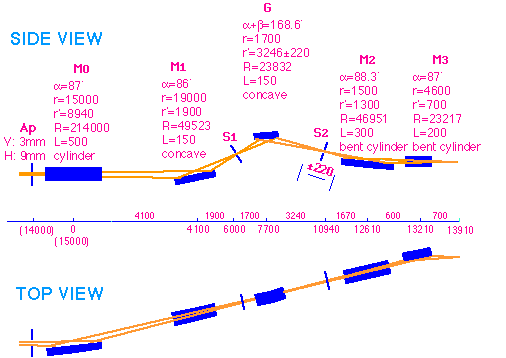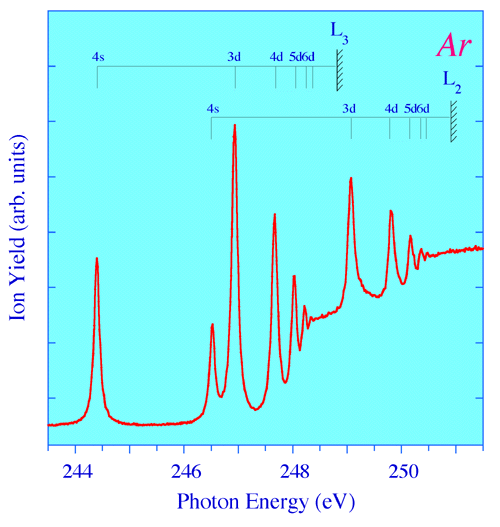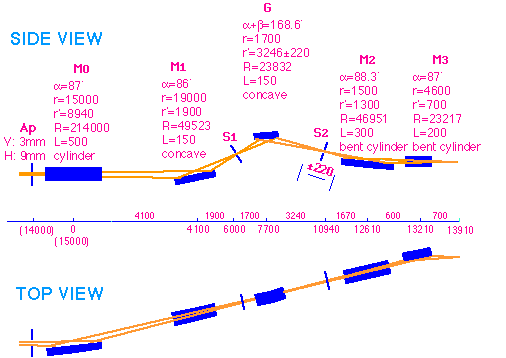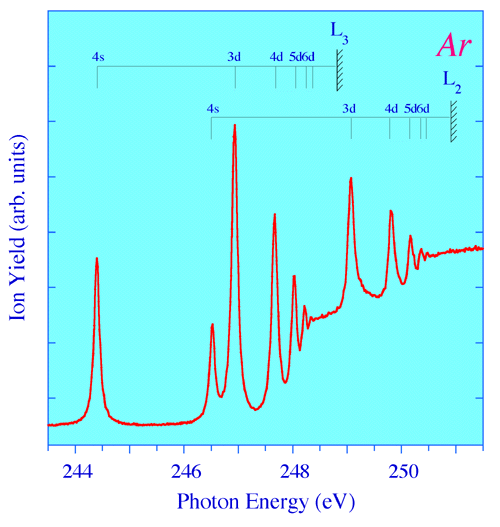BL-16B 高分解能球面回折格子分光器(H−SGM)<<2007/6で閉鎖し、新たなビームラインBL-16Aを建設中です。>>
担当者: 足立 純一
5594(PHS:4348)
adachij@post.kek.jp
1.概 要
本ビームラインは、アンジュレーター放射光の優れた光源特性を最大限活用し、分解能と強度を高いレベルで両立することを目指したブランチビームラインである。分光器は、23.8mの曲率半径を持つ球面回折格子を用いた、いわゆるドラゴン型分光器であり、BL-16のアンジュレーター放射光の特性を考慮して、40eVから600eVの光エネルギー領域を400本/mm、900本/mm、2000本/mmの3種類のシリコンカーバイト製ラミナー型回折格子を用いてカバーするように設計された。”24-m高分解能球面回折格子分光器(24-m
High-resolution Spherical Grating Monochromator; H-SGM)”と称するこの分光器は、微少領域を対象とする実験を実現するため、曲率可変(手動)の後置鏡を有している。
本ビームラインでは、高強度と高分解能が要求される希薄は試料を対象とした実験に適している。
2.性 能
| 光学系 |
M0-円筒鏡/水平集光、
M1-球面鏡/鉛直集光、回折格子-球面、
M2-可変曲率円筒鏡/鉛直集光、
M3-可変曲率円筒鏡/水平集光 |
| エネルギー領域 |
40 〜 550 eV |
| 分解能 |
E/ΔE = 1000 〜 10000 |
| ビームサイズ |
鉛直方向:出射スリット開度とほぼ同じ、水平方向:〜500μm |
| ビーム強度 |
1010 〜1013photons/sec/300mA
(スリット幅100μm→E/ΔE =1000〜2000の時) |
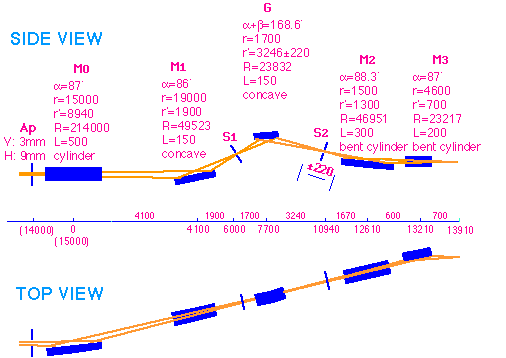
図1.H-SGMの光学系
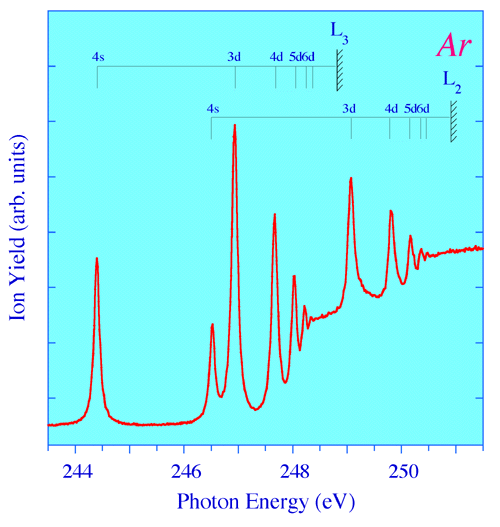
図2.Ar2p光吸収スペクトルの測定例
(分解能は約10000)
3.関連装置
| 波長駆動: |
サインバー方式 (パルスモーターを用いたコンピューター駆動)。分光器の制御は、ビームライン専用のコンピュータで行う。このPCは、RS-232Cにより、ユーザーによる外部コントロールも可能。 |
| 計測システム: |
ORTEC974を用いた標準的なパルス計測システム。ラボ社製ADCを用いた専用PCによるPHA、MCS、GATE、及びLISTモード測定も可能。 |
| 測定装置: |
常置されている測定実験槽はない。実験は共同利用者の持込装置、あるいは共同利用装置を設置してから行うことになる。 |
ビームラインに関しては、簡易マニュアルのみ用意されている。床面からビームまでの高さが他のビームラインとは異なるため、実験装置を取り付ける際には通常高さ可変のスペーサーを使用する。現在2つのスペーサー(各1mx1m)を用意している。16A及びBL-17のX線遮蔽用ハッチとの関係上、実験装置を設置できるスペースが限られているので、注意が必要である。装置の大きさに依っては設置スペースやスペーサーのサイズの不足が考えられるので、担当者に確認して欲しい。
ビームの高さ:〜1367mm 出口フランジ:ICF-114
ビームラインに関する参考文献:
- E. Shigemasa, Y. Yan, and A. Yagishita, KEK report 95-2 (1995).
- E. Shigemasa, A. Toyoshima, Y. Yan, T. Hayaishi, K. Soejima, T. Kiyokura
and A. Yagishita, J. Synchrotron Rad. 5, 777 (1998).
4.実験例
- 原子分子の高分解能分光実験
- 界面の状態を知るための分光実験
- 分子の表面吸着状態に関する分光実験
- アンジュレータ光のコヒーレンス性に関する研究
- 発光寿命の違いを利用した新しい原子分光手法の開発
5.その他
現在2000本/mmの回折格子について、調整機械の不調・反射効率の著しい低下のため、利用をお勧めしておりません。300 eV以上で高分解能を要求される利用者には、BL-2Cの利用をお勧めしております。
Last modified :
2007-10-10