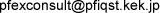結晶(粉末X線回折)
概要---X線粉末回折で何が判るか
大別して二通りの利用法があります。一つは,組成を細かく変化させた大量の試料を用意し,その構造や格子定数の組成依存性を測定する,あるいは,温度変化を非常に細かいステップで測定し,構造などの温度依存性を測定する,という利用法です。もう一つは,相転移後の構造を知りたいが,その相転移によって単結晶が壊れてしまう,あるいはマルチドメインになってしまって単結晶での測定が困難な物質の構造解析です。
最近では,これらに加えて,マキシマムエントロピー法(MEM)による電子密度解析の手順が粉末回折データに対して確立しつつあり,試料の種類によっては電子密度解析を目標に測定を行うことも増えてきています。
測定は概してルーチンワークで簡単ではありますが,試料調製にコツがあり,経験者の助言が必要です。また,解析もルーチンワークではあるものの,偽の解が出ても気づきづらいので,適宜経験者の助言を受けることが重要です。
装置
角度分解能は実験室の装置と同程度である。しかし,放射光の平行性という特性により高角までプロファイルの鈍りが抑えられます。また,全ての2θに対する測定を同時に行う点と,放射光の大強度とが相まって,キャピラリに封じた微量試料で1時間程度のうちに測定が終わるのが特徴です。3日のビームタイムで100以上の試料を測定するユーザーもいます。
10Kから室温まで,あるいは室温から1000Kまでの冷凍機,電気炉を利用し,構造の温度依存性を追跡する実験にも向いています。1時間露光で測定した場合,10Kから室温までを10K刻みで測定すると1日強で,セットアップを含めても3日で測定できます。
高分解能を目指した装置。角度分解能はIP回折計と比べ7倍高いが,測定時間が1桁余計にかかる。大体,一試料あたり12時間が目安となります。また,回折計の構造上,冷凍機の設置が困難であり,試料の温度は100K〜室温の範囲でのみ制御可能です。
IP回折計では分離不能であるピークもこちらでは完全に分離できる事があるので,使い分けが重要です。
Last modified: April 20, 2005 by フォトンファクトリー利用相談窓口